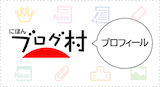今回は就職活動において重要な準備の1つである、「業界研究」について解説していきたいと思います。
業界研究は必ずしもやらなければいけないかと言われると、そうとは言い切れない部分があります。
しかし、就職活動を効率的に進める上で、やっておいた方が良いのは間違いないです!
また、社会に出た後の知識・一般常識として知っておくと役に立つものでもありますので、就職活動が本格的に始まる前の準備として実施しておきましょう。
【この記事の目次】
それでは早速内容に入っていきましょう。
業界研究とは
まず初めに「業界」とは、産業の種類によって企業を分類したものです。
主な業界の種類としては、以下のようなものが挙げられます。
- メーカー
- 卸・小売
- 金融
- サービス
- 通信・ソフトウェア
- マスコミ
そして「業界研究」とは、業界の種類やその特徴を知ること、理解することです。
業界研究はとにかく情報収集だと考えるといいでしょう。その先の行動につなげていくために必要な情報は、早いうちに集めておくに限ります。
業界研究の目的
業界研究の目的は、「効率良く」自分に合った企業を探すことです。
もちろん、自分に合った企業を探すことは業界研究だけで完結する訳ではありません。ただ、そのために重要な手段の1つであると考えましょう。
以前の記事で、就職活動で最初に取り組むこととして「自分の目指すゴールを決めるため」の「自己分析」を紹介しました。
自己分析についての記事はこちら
自己分析で「自分の目指すゴール」を決めたら、それに合った企業を探していくことになります。
しかし、企業は数多くありすぎて1社ずつ見ていくことは到底できません。
そこである程度の絞り込みが必要になります。そのためにまずは、様々な業界について知ることをオススメします!
業態について
効率よく自分に合った企業を探していくためには、業界だけではなく業態についても知っておくと良いでしょう。
業態とは、提供する商品・サービスやビジネスモデルによって企業を分類するものです。
例えば金融業界を例にすると、同じ金融業界の中でも提供するサービスは様々あり、以下のようにいくつかに分類することができます。
- 銀行
- 証券
- 生命保険
- 損害保険
- リース
- クレジットカード など
業界→業態→企業の順に絞り込みをかけていくことで、効率よく情報を集めることができます。(イメージとしては以下の図を参照ください)

上の例では、もっと掘り下げると同じ銀行の中でも、都市銀行/地方銀行/信用金庫のように更に分類することもできますね。
このように業界・業態によって企業を分類し、全体の特徴を掴むということを知っておくだけでも、就職活動を効率的に進められるでしょう。
職種について
就職活動をする際に、よく職種から希望を探す人を見かけます。
「事務職の仕事がしたい!」なんてよく聞きますが、この考え方は果たしていいのでしょうか…?
それは後ほど解説するとして、職種を知っておくことは決してマイナスにはなりません。業界・業態に合わせて、職種の概要を掴んでおきましょう。
代表的なものとしては、以下のような職種があります。
- 営業職
- 技術職
- 企画職
- 事務職
- 販売・サービス食 など
ポイントとしては、総務・人事・経理などの管理部門を除くと、同じ職種でも企業(業界・業態)ごとに違いが出てくることです。
例えば「営業職」言っても、以下の例のように営業のやり方は多種多様です。
- 個人顧客に商品を販売する「B to C型」の営業
- 法人顧客に商品を販売する「B to B型」の営業
- 問題解決を請け負う「コンサル型」の営業
この職種の特徴は、大きくは業界や業態ごとに異なることが多いので、業界研究を行う際に、その業界の主な職種についても調べておくと有益な情報になると思います。
職種を希望する場合の注意点
先ほど、希望職種を中心に就職活動を行うことについて問題提起をしましたが、結論から申し上げますと、これはオススメしません!
なぜなら、企業に就職した後に希望の部署に行けるとは限らないからです。
私が人事で新卒採用を担当している際によく聞いた代表例は、「食品メーカーに就職して商品開発がしたい!」という学生の希望です。
しかし、食品メーカーに入っても商品開発の職種に就けるのはごく限られた人だけで、実際はほとんどが最初は営業職に就くことが多いと聞いています。
実際に私も入社して、研修期間が終わった後に人事部に配属されるなどとは全く思いもしなかったですが、現実はそうなってしまいました。
そんな経験を踏まえて、これから就職活動に望む皆さんに伝えたいのは、「価値観の一致を大切にして欲しい」ということです。
仕事とは自分が会社へ「価値を提供する」ことの対価として給料をもらうこと。
そして会社は社会へ「価値を提供する」ことの対価として売上・利益を得ています。
つまり会社で働くということは、何かしらの形で自分が社会に対して「価値を提供する」ことにほかならないのです。
ですので、社会に対してどのような「価値を提供したい」か、どのような「価値を提供している」企業がいいか、はたまた業界・業態がいいかを考えてみて欲しいのです。
これを企業選びの基準に組み込むことができれば、希望職種に就けなかった場合も前を向いて仕事をしていくことができると思います。
業界研究のやり方
業界研究を実際にやっていくとなった時に、方法はいくつかあります。代表的なものとしては以下のものが挙げられます。
- インターネットを活用する
- 新聞、ニュースを活用する
- セミナー、合同企業説明会を活用する
- 書籍(業界地図)を活用する
この中で、現代で最も手軽なのはインターネットを活用する方法でしょう。まずばここから始めてみるのがいいと思います。
ただし、情報の信憑性は自分でしっかりと判断しなければなりませんので注意しましょう。
また、それぞれの方法にメリット・デメリットが存在しますので、簡単に表にまとめてみました。
この中で、業界研究を行う方法として最も効率的なのは、書籍(業界地図)を活用する方法です。
当然、購入コストがかかってしまうことがデメリットになるのですが、業界研究に特化した情報を収集することができることと、業界間の比較がしやすいことから、業界研究の目的を最短距離で達成できると思います。
一番ポピュラーな業界地図は、東洋経済新報社が出しているものになります。
個別企業を調べる際はこちらもオススメです。
まとめ
最後に振り返りですが、業界研究の目的はあくまでも「効率良く」自分に合った企業を探すことです。業界について調べて終わりにならないように注意しましょう。
また、後々面接対策などで企業の志望動機を考える必要がありますが、
①業界を志望する理由
②業態を志望する理由
③企業を志望する理由
の順で話をするだけで不思議と論理的に聞こえるというメリットもあります。
段々とブレークダウンして考えていくことで、実は「効率的な志望企業探し」と「将来的な面接対策」の一石二鳥になるのです。
業界研究の良いところは、就職活動のスケジュールに縛られないことです。上記のようなメリットを享受するためにも、就職活動が本格化する前に、業界研究に取り組んでおきましょう。
就職活動における考え方と全体像の紹介記事はこちら