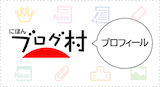積立FXって資産運用の方法として優れているの?
やってみる価値は本当にあるのかな…?

いざ検討してみると、こういった疑問にぶつかります。
実際問題、資産運用の方法が様々ある中で、積立FXが魅力的かどうか判断するのは難しいでしょう。
しかし資産運用は「〇〇が一番良い」というものではなく、自身の運用方針に合っているかどうかが重要だと思います。
私は自身の方針に合致していると思い、かれこれ5年以上「積立FX」をやっています。
今回はその経験を踏まえて、積立FXのメリット・デメリットを紹介していきたいと思います。
積立FXの特徴を理解した上で、検討していただければいいのかなと思います。
【この記事の目次】
ちなみに積立FXとは、FX取引の仕組みを利用して、外貨を積み立てる投資方法です。
詳しく知りたい方は先にこちらをご覧ください。
それでは早速内容に入っていきましょう。
積立FXのメリット・デメリット
まずは積立FXのメリット・デメリットについて全体感を掴みましょう。
積立FXのメリットは以下が考えられます。
- 値動きを細かく気にしなくて良い
- 複利の効果を最大化できる
- レバレッジを活用できる
- 少額から始められる
簡単に言うと、「積立」という特徴から手間がかからないことが大きなメリットの1つです。
また、「FX」の特徴からは比較的元手が少なくて済み、資金効率が良いこともメリットと言えるでしょう。
反対にデメリットには以下が考えられます。
- 損失が発生する可能性がある
- 大きく稼げはしない
- スプレッドが大きい
- スワップポイントの引き出しが難しい
資産運用にはつきものですが、「損失」や「コスト」が発生することを頭に入れておく必要があります。
しかし、あくまでも「積立」という特徴上、FXの中では低リスク低リターンとなります。
リスクとリターンは表裏一体なので仕方ありません。
ここまで概要としてまとめましたが、ここからより詳しく解説していきます。
メリットの詳細について
ではまずメリットについて深堀りしていきます。
先ほど挙げた4つのメリットを1つずつ見ていきましょう。
値動きを細かく気にしなくて良い
FXは市場が常に開いているため、値動きが気になりがちです。
しかし積立FXの場合は、「設定した自動買い付け」以外にほとんど取引をしないので、値動きをさほど気にする必要がありません。
また積立FXは定期的に外貨を購入するので、「ドルコスト平均法」の効果もあります。

一度にまとめて購入すると、「購入のタイミング」による影響が大きく、得をする場合もあれば、損をしてしまう場合もありますが、

「購入のタイミング」分散すると、購入単価を平準化することができ、リスクを抑えることができます。
常に値動きを気にするのは大きなストレスとなることが多いので、初心者には特に重要なメリットだと思います。
複利の効果を最大化できる
2つ目のメリットは「複利の効果を最大化」できることです。
私は積立FXの特徴として、毎日金利収入を得て、それを再投資するという点があると考えています。
試しに南アフリカランドのスワップポイントを再投資する場合と、しなかった場合の利回りの違いを計算してみました。(※2020年10月30日時点)

再投資しない場合は言うまでもありませんが、「毎日再投資」をすると「年に1回再投資」をする場合に比べ、更に高い利回りで運用することができます。
結論としては、複利運用において再投資の頻度は多い方が高いパフォーマンスが出るということです。
レバレッジを活用できる
先ほどの運用利回りはレバレッジが1倍と仮定して計算したものになります。
仮にレバレッジを2倍にしたとすると利回りは以下のように変わります。

単純に先程に比べて2倍の利回りになっています。
レバレッジはリスクにもなりますが、それと同じだけのリターンにもなります。
リスク管理に気をつけてうまく活用すれば運用効率を上げることができます。
このあたりの計算については、より詳しく以下の記事で解説しています。
少額から始められる
積立FXは、元手が非常に少なくても始めることができます。
本当に始めるだけならば、10円くらいからできてしまいます。
なぜならば、積立FXでは「1ヵ月間の最低購入単位が1通貨」 となっているからです。
ただ実際には、上記はあくまでも極端な例ではあるので、現実的には「1,000円/月」くらいからだと考えておくと良いでしょう。
いずれにせよ、少額から手軽に始められるのも積立FXの大きなメリットの1つです。
詳細は以下の記事をご覧ください。
ここまでメリットを解説してきましたが、半自動的に運用でき、少額から始められる積立FXは初心者にも向いているのではないかと思います。
FXの取っ掛かりとしては個人的におすすめです!
しかし、まだメリットしか見ていませんので、反対にデメリットも確認しておきましょう。
デメリットの詳細について
今度はデメリットについて深堀りしていきます。
こちらも最初に4つ挙げましたので、1つずつ見ていきましょう。
損失が発生する可能性がある
値動きがあるので、当然損失が発生することがあります。
私は積立FXを取り組み始めてから3年以上経っていますが、含み損を抱えている場面もありました。
また、獲得できるスワップポイントが変動するため、メリットで紹介した利回りも変動する可能性があります。
私が実際に取り組んでいる運用実績も公開しておりますので、よろしければご覧ください。
私の場合は長期的な運用を考えていますので、スワップポイントを獲得しつつ、着実に資産を増やしていこうと思っています。
しかし、短期的な運用をされたい方や、すぐに必要となるお金を元手にする場合にはおすすめできません。
大きく稼げはしない
基本的に値動きに対して売買を行って稼ぐ投資スタイルではありません。
またレバレッジも、多くのFX取引が上限25倍であるのに対し、積立FXは最大でも3倍となっています。
積立FXは長い目で見て一定の利回りで稼ぐ方法ですので、 大きな利益を短期間で得ることは難しいです。
取り組む上では、我慢強さも必要になるでしょう。
スプレッドが大きい
通常FXでは「買値」と「売値」に差があって、その差を「スプレッド」と呼んでいます。

この「スプレッド」があることで、上の例だと買った瞬間に同値で売ったとしても、「1ドルあたり0.05円損をする」ことになります。
つまり「スプレッド」は取引をする際のコストとなるわけです。
また、この「スプレッド」分がFX業者の収入となっています。
その「スプレッドが大きい」=「コストが大きい」ことが積立FXのデメリットとなります。
スプレッドの詳細は以下の記事をご覧ください。
これに関しては、積立FXを使いたいならば、サービスの対価として割り切るしかありません。
「スプレッドが高い」ことが嫌ならば無理に使う必要はないでしょう。
しかし、外貨預金と比較すると、積立FXのスプレッドはむしろかなり小さいです。
外貨預金を検討するくらいなら、積立FXを考えてみると良いと思いますよ。
外貨預金と積立FXの比較について、詳細は以下の記事でご覧ください。
スワップポイントの引き出しが難しい
「SBIFXトレード」と「SBI証券」においてスワップポイントは「評価損益」に含まれる仕組みとなっています。
日々変動する「為替差益」と合算されるため、スワップポイントの利益として管理するのがやや難しいのです。
しかし、本質的なルールとしては、「スワップポイント」と「評価損益」を含んだ「証拠金」から「取引に必要な証拠金」を差し引いた金額が引出し可能です。
(ただし、評価益が膨らんだ場合でも、引き出し可能な金額は現金で入金した金額と利益を確定した金額の合計上限となります)
詳細はこちらをご覧ください。
考え方や証拠金の管理が難しいだけで、しっかりと理解さえできれば大きなデメリットにはなりませんので安心してください。
以上が私の考える積立FXのデメリットです。
当たり前といえばそれまでですが、実際に運用する前に頭に入れておく必要はありますね。
私の運用方法
私は積立FXのメリットを活かした運用方法を実践しています。
参考までに実際に継続している運用方法を簡単に紹介します。
私は「スワップポイントを毎日再投資する」ことを積立FXで実現しています。
積み立てをするには「元手となる資金」が必要となりますが、その資金を「一定の通貨を保有し、そこから得られるスワップポイント」で賄っています。
以下、私が実際に実施した手順です。
- スワップポイントを獲得するため通貨を購入
- スワップポイントを獲得
- 積立FXの設定をする
この手順について、より詳しくは以下の記事にまとめています。
毎日得られる「スワップポイント」を「再投資する」ことが、複利効果を大きくするポイントだと思っています。
よろしければ参考にしてみてください。
まとめ
私は6年以上「積立FX」を継続しており、その中で感じたメリット・デメリットをお伝えしました。
実際やってみて、6年以上簡単に継続できたということが1番のメリットなのかなとも思っています。
資産運用の成果は「資金」✕「利率」✕「時間」で測れると考えていますが、前提となるのは続けることです。
そういった意味では、資産運用の一環として取り入れても良いのではないでしょうか。
ちなみに現在、積立FXのサービスを取り扱っているのは「SBIFXトレード」と「SBI証券」の2業者となっています。
ちなみに私は「SBI証券」の口座で積立FXの取引を行っています。
また、2つの業者の特徴を比較した記事もありますので、検討する際はぜひご覧ください。
「積立FX」はもちろん、「通常のFX」や「外貨預金」等の運用を考えている方にも参考になれば嬉しく思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。